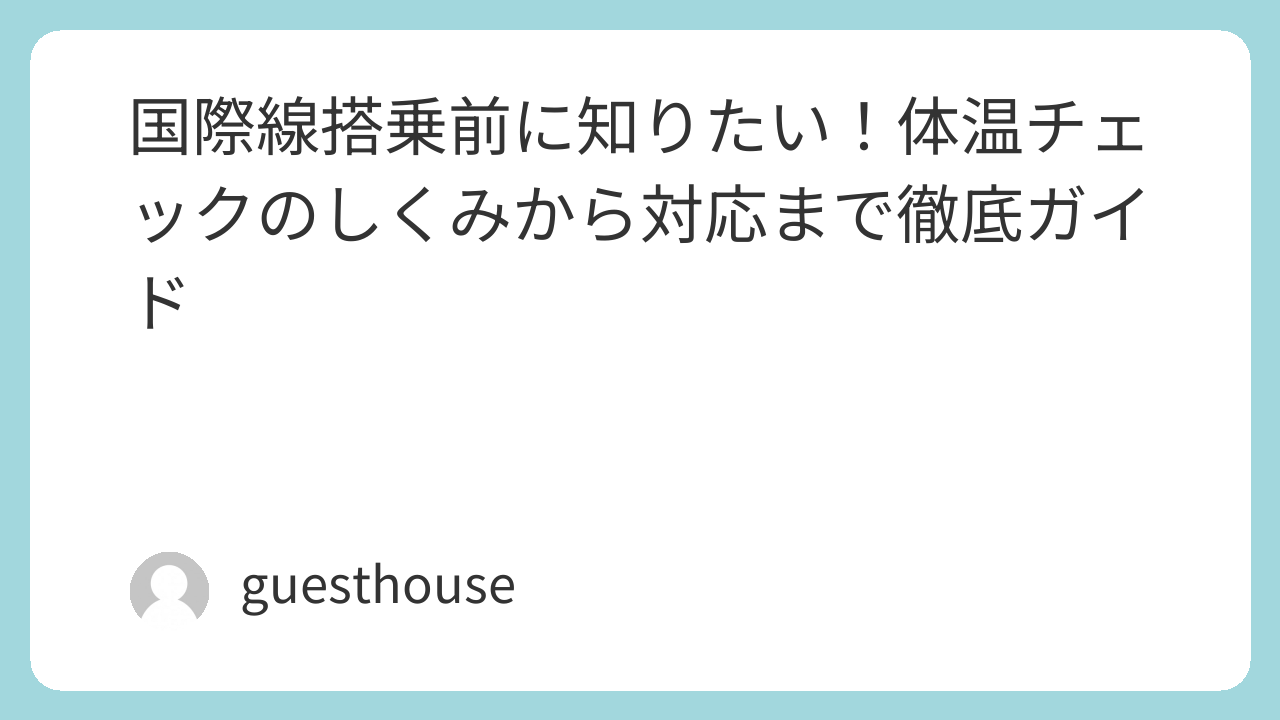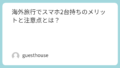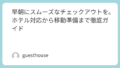国際線に乗る際、現在でも体温チェックは実施されているのか、どんな方法で、どのタイミングで行われるのか気になる方も多いはずです。
本記事では、サーモグラフィーやハンドヘルド体温計などの測定手法、主要国内空港や海外空港における実態、発熱時の搭乗・入国への影響、さらには空港で熱がある場合の具体的な対処フローまで、体系的に解説します。
安心して旅を続けるための準備にお役立てください。
国際線で体温チェックはあるのか?どんなチェックをされる?
国際線を利用する際、実際に空港でどのような体温チェックが行われているのか、不安を感じる方も少なくありません。
ここでは、最新の状況として、非接触型の体温スクリーニングの仕組みや運用状況、安全への配慮からどのような体制が整えられているのかをご紹介します。
サーモグラフィー(非接触型赤外線カメラ)の仕組み
多くの主要空港では、非接触で体温を測定できる赤外線サーモグラフィーが導入されています。
この技術により、多数の利用者をスムーズにスキャンし、発熱の可能性がある人を迅速に識別することが可能です。
例えば、羽田・成田・中部・伊丹・関西・福岡の主要6空港では、出発前にこの方式による体温測定が継続的に行われています。
ハンドヘルド体温計による測定の実施状況
サーモグラフィーで異常が検出された場合、さらに精密な測定のためにハンドヘルド式の非接触体温計が用いられます。
この方法は測定精度が高く、発熱の判断やその後の対応を確実にするために役立ちます。
体調不良と判断された場合には、医務室への案内やさらなる対応が取られることが一般的です。
検温が行われるタイミング(チェックイン/保安検査/搭乗口など)
体温チェックは、チェックインカウンターや保安検査場の入口、さらには搭乗口など、出発前の複数のポイントで実施されることが多いです。
空港によっては、チェックイン直後から搭乗手続きまでの間に複数回測定が行われ、早期発見と安全管理が強化されています。
これにより、搭乗前の早い段階で体調不良者を特定し、適切な措置を取ることが可能です。
体温チェックの精度や基準温度(例:37.5℃以上)
日本の多くの空港では、37.5℃以上の体温が発熱の基準として採用されており、37.5℃を超えると発熱とみなされるのが一般的です。
この基準に沿って測定が行われ、発熱が確認された場合には搭乗を控えるよう要請されます。
このような措置は、他の乗客や乗務員の安全を守るために欠かせない予防措置です。
測定結果に応じた追加対応(再測定/医務室への誘導など)
サーモグラフィーで異常が検出された場合、まず再測定が行われます。
それでも体温が基準を超えている場合は、医務室や健康相談窓口などに案内され、必要に応じた問診や診察が実施されます。
場合によっては航空会社の搭乗条件に照らし、搭乗の自粛や延期の手続きがすすめられることもあります。
乗客側が把握しておくべき注意点・自己管理のポイント
旅行前には自身で体温測定をし、体調に異変があれば早めに対応することが重要です。
発熱や体調不良があるにもかかわらず搭乗を強行すると、本人だけでなく周囲の安全にも重大なリスクを及ぼします。
そのため、健康状態に不安がある場合は、診断書の用意や航空会社への事前相談を検討するなど、慎重な行動を心がけましょう。
日本の主要空港(羽田・成田・中部など)における国際線体温測定の実施状況
主要空港での出発前の健康確認は、旅行者にとって安心の重要な要素となっています。
ここでは、羽田・成田・中部・伊丹・関西・福岡の空港で導入されているサーモグラフィーによる体温測定の状況や、どのような形式で実施されているのか、ガイドラインや運用の違いに着目して整理します。
実施空港リスト(羽田・成田・中部・伊丹・関西・福岡など)
日本の主要空港では、国際便を利用する乗客向けにも非接触体温測定が導入されています。
具体的には、羽田、成田、中部、伊丹、関西、福岡の六つの空港が対象です。
これらの空港では、出発時点での健康確認としてサーモグラフィーによるスクリーニングが行われており、異常があった場合には追加対応も設定されています。
国土交通省や空港ビル協会によるガイドライン
国土交通省と全国空港ビル事業者協会は、新型コロナ対策として包括的なガイドラインを策定しています。
このガイドラインには、各空港における体温チェックの体制整備や、感染リスクに応じた対応方法が明記されています。
旅客の安全を確保するため、これらの勧告に基づく運用が全国の空港で導入されています。
測定実施の現状(常設か、状況に応じた臨時か)
例年、羽田と伊丹では常設の体温測定体制が敷かれていますが、他の空港では必要に応じて臨時体制で導入されるケースも多くあります。
成田、関西、中部、福岡の空港では緊急時や特定の期間に、国内線保安検査場の入口などでサーモグラフィーを設置して対応する体制が見られました。
現在のところ、国際線に関しては状況に応じた運用の傾向が続いており、常設化には至っていない場合もあります。
測定結果への対応方法(搭乗取りやめ要請など)
サーモグラフィーで37.5℃以上の体温が検出され、なおかつ咳や倦怠感などの症状がある場合、搭乗の自粛を要請するケースがあります。
こうした対応は、航空会社の運送約款に基づいた措置として行われ、安全確保を目的としています。
また、結果に応じて健康相談窓口や医務室への誘導が行われることもあり、柔軟に対処できる体制が整えられています。
海外(他国)空港での国際線体温チェックの動向・事例紹介
海外の空港や航空会社においても、出発前の体調確認は旅行者に必要な安心を提供する一環として導入が進められています。
本セクションでは、各国や主要キャリアにおいて採用された取り組み、使用される体温測定技術の差異、基準となる温度設定の目安、さらには緩和傾向が見られる地域に関する最新動向をまとめます。
各国・航空会社の導入事例(例:Air France, Singapore Airlinesなど)
Air Franceでは、2020年5月より接触を避けた赤外線体温測定を段階的に導入し、38 °Cを超える場合は搭乗不可とする方針を示しました。
Singapore Airlinesでは、出発前の健康状態も含めたアセスメントとともに、99.5 °F(約37.5 °C)以上の体温測定がある場合は搭乗が認められませんでした。
カナダのAir Canadaでも、チェックイン時にタッチレス体温測定を行い、99.6 °F(約37.6 °C)以上の場合には搭乗を制限しています。
温度チェック技術の違い(赤外線キオスク vs ハンドヘルド)
多くの空港では、赤外線カメラによる非接触式スキャンが、搭乗ゲートや保安検査場などで初期スクリーニングに活用されています。
一方で、発熱の疑いがある場合には、より精度の高いハンドヘルド式の非接触体温計による再測定が行われる場合が多く見られます。
このように、スピーディな初期検査と正確な再測定を組み合わせた二段階方式が、海外でも採用され始めています。
測定基準温度の目安(例:38 °C や 100.4 °Fなど)
基準となる発熱温度は、国や航空会社によって異なりますが、100.4 °F(38 °C)を超えた場合に搭乗を拒否するのが多くの国で見られる基準です。
Air Franceでは、この38 °Cを超える体温で搭乗を拒否する方針を明確に打ち出しています。
また、アメリカやその他の地域でも100.4 °F を境にした対応が一般的であり、世界的な目安として定着しつつあります。
一部緩和されている国・空港の現状(例:南米など)
一部の地域では、感染状況や社会的ニーズの変化に応じて、体温確認プロセスを簡略化または一時的に緩和する動きも出始めています。
ただし、南米などの具体的な緩和事例に関しては、最新の公開情報が少なく、現在も導入継続中のケースが多く見受けられます。
今後の動向としては、感染拡大の収束やワクチン普及の進展に合わせて、各国の対応がさらに柔軟化される可能性があります。
体温が高かった場合、搭乗や入国にどう影響する?判断基準と対応
国際線で体調に異変があった際、特に熱がある場合には搭乗や入国の可否に重大な影響を及ぼすことがあります。
このセクションでは、発熱が確認された場合の一般的な対応、航空会社や国によって異なる取扱い、医師の関与が求められるケース、さらには検疫や入国手続きでの対応までを詳しく見ていきます。
発熱(例:37.5℃以上)が確認された場合の原則対応(搭乗控え要請など)
通常、37.5℃以上の体温が検出された場合、搭乗を控えるよう要請されるのが一般的です。
多くの航空会社や空港では、感染症リスクの拡大を防ぐ観点から、このような対応を定めています。
アメリカでは「100.4°F(約38°C)」以上の発熱があると搭乗を拒否するケースも報告されており、安全確保のための基準として用いられています。
航空会社ごとの対応例(診断書提出で搭乗可の場合も)
航空会社によっては、発熱がある場合でも医師の診断書を提出することで搭乗が認められる場合があります。
ただし、これは例外的な対応であり、多くのケースでは判定基準をクリアしなければ搭乗不可となります。
また、アメリカの規定では、明らかな伝染病の兆候がある旅客は搭乗を拒否されることが合法とされており、航空会社には広範な裁量権が与えられています。
医師相談や診断書取得の意義と必要性
医師への相談や診断書の取得は、体温異常が健康上の一過性のものであることを証明する助けになります。
特に病歴や薬の影響などによる一時的な発熱の場合、搭乗可否の判断材料として有効です。
しかし、公的なガイドラインでは、医師の診断があっても「直接的な脅威(direct threat)」と判断されれば搭乗が拒否される可能性があることに留意が必要です。
入国審査や検疫での対応(入国拒否や隔離の可能性など)
入国審査や検疫の場でも、発熱が確認された場合には入国拒否や隔離措置が取られる恐れがあります。
特に感染症の流行期には、指定された空港で一定の待機や追加検査が求められることがあります。
世界保健機関(WHO)の推奨事項でも、発熱などの症状がある旅行者には旅行の延期を促す内容が含まれています。
空港で熱があるとどうなる?プロセスと対処法
発熱など体調不良が疑われる際、空港ではどのようなサポートと手続きがあるのかを把握しておくことは非常に重要です。
ここでは、医務室での対応プロセスや問診票などの健康確認方法、保険や診断書を活用した手続き変更の流れ、体調が頑なに優れないときの具体的な行動まで、出発前に知っておきたい対処法を体系的にまとめます。
医務室・健康相談窓口での対応フロー
空港内で発熱が疑われると、まず医務室や健康相談カウンターへ案内されることが多いです。
専門スタッフが問診や体温測定を行い、必要に応じて医師への引継ぎや追加検査へ進みます。
場合によっては、症状に応じた指示や隔離待機など、安全を確保するための対応が取られます。
自己申告と追加健康チェック(問診票提出など)
発熱や体調不良を自覚している場合には、自己申告と問診票の提出が求められることがあります。
問診票には症状や最近の接触歴、渡航歴などが記され、それを基に保健当局や航空会社が状況を判断します。
このプロセスは医師による判断に至る前の重要な情報収集となります。
保険対応や診断書提出によるキャンセル/変更対応
体調不良で搭乗が難しい場合、公的・民間の旅行保険が適用されるケースもあります。
また、医師の診断書を提出することでキャンセル料が免除されたり、航空券の変更が認められる場合もあります。
ただし、航空会社の判断や規定により対応に差があるため、事前に確認しておくことが安心につながります。
頑な体調不良時の対策(航空会社連絡・旅行延期など)
熱がある状態で無理に搭乗しようとせず、まず航空会社へ直ちに連絡を取りましょう。
旅行の延期や振替を検討することは、自身の健康と他の乗客の安全を守る観点から非常に重要です。
自己管理だけでなく、周囲に迷惑をかけないための勇気ある判断も、旅行者としての責任です。
まとめ
本記事では、空港での体温検査の仕組みや運用パターン、国内外の対応状況に加え、発熱時の搭乗判断や入国審査での扱い、体調がすぐれない際の具体的な対応策までを幅広く解説しました。
非接触型カメラやハンドヘルド検査の精度や基準、国内の主要空港での導入状況や規制当局の方針、さらに海外空港での実例まで、包括的に把握いただけたかと思います。
万が一熱がある場合の流れや医師相談、診断書の活用方法、さらには旅行保険や航空会社への連絡などを踏まえ、安全な国際線搭乗の準備を整えていただければ幸いです。